
こんにちは
今年中には一度マラソンにチャレンジしてみたいと思っている
ボクシング&フィットネストレーナーの井上です。
久しぶりに走ると息があがるのが早い事にショックを受けてますが、走る時だけじゃなくボクシングでもハードに練習していると息があがってきますよね。
呼吸が乱れると正常な判断がしずらくなったり動きが遅くなります。
なるべくなら素早く呼吸を戻したい。
そんな時どんな事を思いますか?
おそらく「酸素が欲しいから息を出来るだけ吸いたい」という答えが多いんじゃないでしょうか?
でも、ちょっと待ったー。
それは酸素を取り込むためには逆効果。
逆に息を吐いた方が二酸化炭素と酸素のガス交換が高まります。
それは「死腔」と呼ばれる場所が影響しているからです。
もくじ
死腔とは
肺と喉、口をつなぐ気管支。
この気管支の容積のことを「死腔」と呼びます。
なぜ人体の中に死という文字が使われているのか?
不思議ですよね。
もちろん、ちゃんと理由があります。
例えば人が300mlの息を吸った時、すべての空気は肺胞(気管支の末端でここでガス交換が行われる)に到達しないんです。
この間に気管支があり、気管支を通らないと肺胞へはいけません。
ここで気管支の容積が100mlだとすると肺胞に無事にたどり着けるのは200mlだけ。
死腔の容量が大きいと呼吸の効率が悪くなります。
気管支は呼吸の役にたっていないため「死腔」とよばれることに。
息があがった時に吐く理由
ここで運動して息があがった状態を思い出してください。
息を「吸う」ことに意識が向かって細かい呼吸になっていませんか?
先程書いたように入ってくる空気の量が少ないと死腔があるため肺で十分な空気交換が行われません。
吸っても上手く交換できないから、また素早く吸おうとして呼吸が落ち着くのに時間がかかります。
多くの空気を体に取り入れるには、体に空気が少ない状態の方が入ってきやすくなります。
そこで「吐く」が大事になってきます。
口からは長く吐き、鼻から大きく吸います。
運動中であれば素早く吐ききり、鼻から素早く大きく吸います。
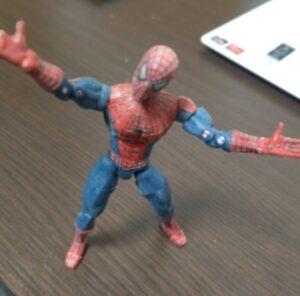
「好きになる生理学」という本の中で死腔について分かりやすい例があります。
ホースを口にくわえて口で息をする。ホースの内容積が300mlだとしたら息を300ml吸っても吸えるのはホース内の空気だけ。そして息を300ml吐いても吐いた息はホース内に留まります。新鮮な空気が吸えないので息苦しさを感じます。
このホースの部分が「死腔」です。
初めての人でも読みやすいです。
試合中や練習中で呼吸を速く回復したいときは、深い呼吸を。
またその時「吐く」ことを意識して入ってきた空気とがず交換できる量を増やし、早く呼吸を回復させていきましょう。
こちらのブログでも呼吸について書いてます。
関連ブログ
「ボクシングを始めたばかりでもっと上手くなりたい」、「ゆっくりとミット打ちや技術を習いたい」、「やったことないけどミット打ちをしてみたい」などありましたらお任せください。またボクシングだけでなく、身体の使い方や筋力トレーニング、食事管理サービスも行っています
詳しくはパーソナル料金
毎週木・日曜日には横浜元町でボクシング教室を開催中
ボクトレ教室
一言日記
ゴロフキンが来日しましたね。
まさかあのゴロフキンが日本で試合する日が来るとは思ってもいなかった。
強いゴロフキンもみたいし、村田選手が勝つ所もみたい。
4月9日が待ち遠しい


